| |
|
|
 |
| |
|
|
| |
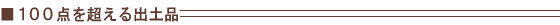 |
|
| |
|
|
| |
王塚古墳は昭和9年に発見されるまで未発掘の古墳であったため、豊富な副葬品の大部分が残されており、その数は100点を超えます。現存するものはすべて国の重要文化財に指定されています。
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
【馬具】
王塚古墳からは「鞍」「輪鐙」「杏葉(ぎょうよう)」などの馬具類が多く出土しており、その造りの緻密さ、豪華さは日本でも有数のものとされています。
王塚古墳の石室に馬の絵が描かれていることも関連して、王塚古墳の出土品とし代表的なものです。 |
|
| |
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
鐙
(あぶみ) |
杏葉
(ぎょうよう) |
轡 (鏡板)
(くつわ) |
雲珠
(うず) |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
【鏡・装飾品】
「変形神獣鏡」も王塚古墳の代表的な出土品の一つです。この裏面には鏡を包んでいたらしい麻のような布が付着しており、当時の人々の布地の材質を探る手がかりにもなっています。
また、鏡とともに「管玉(くがたま)」「棗玉(なつめだま)」「切子玉(きりこだま)」「小玉」「耳環(みみわ)」「銀鈴(ぎんれい)」などの装飾品も出土しています。
なかには、埋木(石炭)で作った玉などもあり、この地域独特のものとして興味深い出土品といえます。 |
|
| |
|
|
| |
 |
上段左より
土製丸玉、管玉、銀の鈴
下段左より
埋木製切子玉、コハク製なつめ玉、金の耳輪 |
 |
変形神獣鏡 |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
【武具・武器】
鉄製武器・武具としては「大刀」「鉾(ほこ)」「刀子」「鉄鏃(てつやじり)」などの武器や「挂甲(けいこう)」(鉄製の小片をとじあわせて作られたよろい)の小札(こざね)などが副葬され、当時の緊張した社会情勢を推測することができます。 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
 |
|
| 大刀 |
|
挂甲(けいこう)の小札(こざね) |
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
【土器】
前室からは古墳時代の代表的な土器である「土師器」「須恵器」が見つかっています。
「土師器」は弥生式土器の技法や感覚を受け継ぐもので、野窯により比較的低温で焼かれているのに対し、5世紀ごろから登場してきた「須恵器」は、穴窯により
1200~1400度の高温で焼かれたガラス質に近い土器です。
王塚古墳からは「須恵器」として杯類や壺類などが多く出土しています。 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
|
須恵器
台付壺 |
|
須恵器
坏と蓋 |
|
須恵器
提瓶(さげべ)
高坏(たかつき) |
|
|
|
| |
|
|
| |
>>古墳発見物語へ |
|
| |
 |
|
| |
|
|

